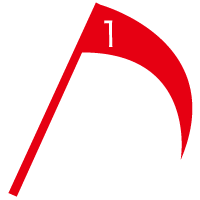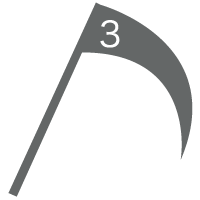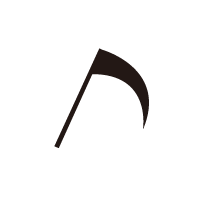熊坂 出
わらわらざわざわと子供達。学校で一番ドキドキする時間が始まった、と香は思った。それはつまり帰りの会のこと。
「今日三時タマリバ!」「オッケー!」「今日、そよの家でアサシンしようぜ」「いいぜー!」香が目を閉じて耳をすませば、教室を超え廊下を超え校門を超えて、路地で遊ぶ子供達の風を感じとることができた。今はもう7月だけれど、夏休みはなかなかやって来ない。ただただ暑くてその暑さは皮膚を刺す。夕方にならないと暑くて痛くて外で遊べない8月はまだ先。もう充分暑いけれど、沖縄はまだまだもっともっと暑くなる。香は目を開けて、負けじと新しくできた友達に声を掛けた。
「マオ!」
「キョウハ、マオ、ダンスレッスン、デス! じゃ!」
マオはマッハで教室を飛び出して行った。「香ちゃん、今日遊べる?」と順子が声をかけてくれたけれど、「同情すか?」と香は言って、順子の優しさを台無しにした。そして香は一人になった。
香は今から一ヶ月前、那覇市識名にあるアパートから那覇市おもろまちにあるアパートへ引っ越してきた。那覇よりもずっと北にある北中城に引っ越そう、田舎暮らししよう、と母親のスミレは言っていたのに、引っ越し先は識名からチャリで10分のところにある近場のおもろまちになった。理由はスミレの気が変わったから。おもろまちは新興住宅地で識名に比べてこざっぱりしている。けれど、沖縄の匂いのする風は変わらない。
おもろまちの新しい家に帰った後、香はチャリに乗って那覇中央病院にやって来た。
中庭のベンチに座って、リハビリに励む松葉杖のおっさんや、タバコを吸っている黄疸の目をした入院服のおっさんを眺めながら、香は二ヶ月前に路地で知り合ったガキンチョの事を思い出していた。名字は忘れた俊太のこと。香は5分程ぼーっと過ごすとベンチから立ち上がって、駐輪所へ向かって歩き出す。
病棟の脇のコンクリートの道を歩いていると、風も前触れもなく一枚のカードが空から降って来た。香が拾い上げるとそれはアサシンモンスターカードで、フェニックスくんという名のモンスターが描かれていた。見上げると「持って来て!」と叫ぶ入院患者がいた。3階の窓から上半身を乗り出しているそのガキンチョは小さくてよく見えなかったけれど、とにかくそれが香と健太の出会いだった。
「俺は末期がんなんでしょ」
「いい加減にして!」
香の耳に入って来た二つの言葉。最初のが健太の言葉で、最後のが健太の姉の言葉。健太の姉はその言葉を吐き出して病室から出て来る。香の目には中学生くらいに見える。健太の姉がいなくなると、香は病室へ入っていった。
病室は6人部屋。健太のことはすぐに分かった。向かって左手にある窓際のベッドに腰掛けていたから。他のベッドはカーテンで仕切られて見えなくて、カーテンが開けっ放しになっている右手真ん中のベッドには、おじいちゃんが寝ていた。おじいちゃんは終始かすかに震えながら、たまに、ううううとかうあああとか声を上げる。
健太のベッドの窓際にはアサシンモンスターのぬいぐるみが飾ってある。香はアサシンモンスターには全く興味がなかったが、それでもそのぬいぐるみがアサシンモンスターだとは見てすぐに分かった。南青山にいた頃、小学校でもアサシンモンスターカードがものすごく流行っていて、男子が皆アサシンモンスターカードゲームをやっていたから。そのぬいぐるみは、背中に大きな種を携えた緑色のデブ猫みたいに見える。
「この猫なんて名前」
「猫じゃないよ、バカダネ」
香は拾ったアサシンモンスターカードを健太に手渡す。健太は母親が3分くらいでカットした無造作な短髪で、夕飯やら鼻水やらのシミで灰色がかった水色のパジャマを着ている。大きな目、真っ赤な鱈子唇。
「ありがとうと悲しい話どっち聞く?」
健太がそう言うので、なんかちょっと俊太っぽいなと香は思った。
「どっちも聞きたくない。じゃあ」
うああああ、と向こうのベッドの老人が思い出したように口を開ける。看護士がやって来る気配はない。香は心配になったというより、怖くなった。
「あのおじい、俺、嫌だ。ご飯もこぼすし」と健太は小声で言った。
「やめなよそういう事言うの」
「なんで?」
「失礼じゃん」
「なんで?」
「なんでって」
健太は話題を逸らすように顔をバカダネに向けた。
「小2ってさ、世間知らずさぁ? 俺だけじゃないよね?」
「…それを言ったら、子供は皆世間知らずなんじゃないの」
「でもさあ。子供ん中でもさあ。小2って、なんにもないよ。ずるさとか。俺だけかもしれんけど」
香は何も言わない。
「アサシンモンスターカードゲームチャンピオンシップ九州大会申し込みハガキを一通出したんだよ。沖縄はやってないから」
香は黙って聞いている。うあああああ。
「絶対当たるって思ってたけど、外れた。小3の時、少しずるくなってハガキを3枚出したんだよ。一番上の兄ちゃんがずるを教えてくれたから。でも当たらなかった」
香は話を聞くのが段々面倒になってきた。
「小4の時は10枚出したけどやっぱり駄目だった。それで今年、何枚出したと思う?」
香は黙っていた。でも、黙っているのを止めて「1000枚」と言った。
「ええ? そんなの無理だろ!」
香は帰りたくなって俯いてため息をついた。
とその時、香は唐突に今朝の母親の言葉を思い出した。「ボサツのこころ」というスミレの言葉。
あたしねえ、もっともっとそれこそ香ぐらいの時から、菩薩の心でいる事を意識してたら、今の年齢でもっともっと大人になれてたと思うのよね。今更そんなこと言ったって意味ないんだけど。
今朝、ご飯を食べながら母親のスミレは香にそう言った。
香は「ボサツの心」とお腹の中で唱えた。あたしはお母さんと違って、もっと普通の人生を送れるようになりたい。ボサツの心、ボサツの心、ボサツの心。
香は帰る代わりに尋ねた。
「何枚出したの?」
「30枚。そしたら、出場権が当たったんだ。倍率100倍だった。だけど、盲腸になって出場できなくなった」
「盲腸?」
「盲腸」
「ふーん」
「ふーんって言うな」
ふーんで充分じゃん、と香は思う。そこらへんに落ちてる言葉で充分じゃん。
「お前、何小?」
「
「真赤火か。遠いな。俺は
香は、今日のテーマをたった今、決めた。
ボサツの心。ボサツの心だ。
よって怒るのはなし。
「もし一緒に遊んで欲しいんだったら、カードゲームの相手になってあげるよ」
香は、提案した。
けれど、健太は何も答えない。
それどころか、横になって毛布の中に潜り込んでしまった。
「やんないの?」
「俺にとってこれは遊びじゃないし」
「じゃなんなの」
「人生」
大げさな言葉に、香はもう心が折れそうになった。
まだ10年くらいしか生きたことないくせに。
「俺の全人生をかけた大勝負だったんだ、今度の大会は」
「知らないよそんなの。やるのやらないのどっちなの」
少し沈黙があった後、やんねえよ、と健太が言った。
「だって今更やってもどうせ大会に出られない」
健太の声は切実だったし、その悔しさや悲しみは香に届いた。
「神さまなんていないし!」
健太は泣いていた。
香は、健太がどれだけ大会に出たかったのかが分かった。のだけれど、香は心を動かされることはなかった。
香は病室を出ようと、振り返る。
その時、香は視界の中に何かを見つけた。
バカダネのぬいぐるみが置いてある窓際の、窓の向こう。
向かいの病棟にある病室の窓際。
健太が持っているのと全く同じバカダネのぬいぐるみがそこにあった。
香の目の先を追って、健太も気付く。
「マジか! バカダネだ!」
「あんた入院してて気がつかなかったの?」
「何歳くらいの奴かな」
「入院してる人?」
「うん。意外と大人かも。お前どう思う?」
香はそれに答えず、病室から出ていこうと歩き出す。
「どこ行くば?」と健太。
「帰る」
「カードゲーム一緒にやるって言ったのはどこのだれよ」と健太が呼び止める。
最初から素直になんなよ小2じゃないんだから。
そう簡単に人生捨てちゃいけないよな。
俺、宮里健太。
私、谷川香。
続く