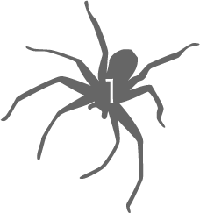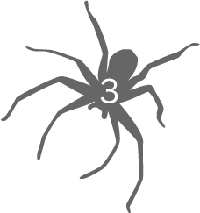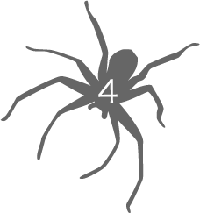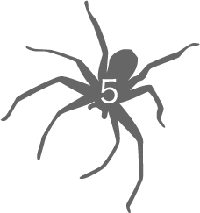熊坂 出
「今日って何の日か知ってる?!」
「知らない!」
「マリリンモンローが死んだ日!」
「誰それ!」
「あんたマリリンモンロー知らないの?!」
「全然全く聞いた事もない!」
「あんた母子家庭なんだから、マリリンモンローの伝記くらい読んでおきなさい!」
香とスミレは今、フェリーの上。エンジンの音と波の砕ける音がとっても大きくておしゃべりが怒鳴り合いになる。
2人は
その2人の近くに、陽に焼けた少年が一人で座っている。少年の目は狐のように細く、髪の毛は短くスポーツ刈りに刈り揃えてあった。少年は香と目が合うと咄嗟に目を逸らした。少年が香のことを意識しているのはすぐに香に伝わり、それで香もまた少年のことを意識してしまう。香の目から見ると、少年はどうひいき目に見てもカッコいいとは思えないのに、どこか他人の目を意識している自意識過剰な男子に見えた。なんでこんなヤツを意識しなくちゃいけないの、と香は自分に苛立つ。
スミレがリュックの中から一枚のプリントを出して香に手渡した。
「はいこれ! 久高島の地図」
*
9時15分に久高島に到着した。
スミレのお目当ては「うぷうがみ」だった。
うぷうがみは元々男子禁制の場所だったけれど今は立ち入り禁止で誰も中に入れない。でも中に入れなくてもいいから、その森を外から眺めてみたいの。
2人は港から歩いて1分のところにあるレンタサイクル屋へ入った。お店には誰もいない。スミレは500円玉を2枚カウンターに置くと、チャリを適当に見繕う。
「ねえ、お母さん」
「なに?」
「この島、あんまり人がいないね」
「交番もないんだってよ」
「え? ガチで?」
「うん」
2人がレンタサイクル屋を出ると、島の子供達とすれ違った。小学校低学年の男の子達は、こんにちは、と気持ちのいい声で挨拶をして来た。こんにちは、とスミレと香も挨拶を返した。挨拶をするのはやっぱり気持ちがいいね、とスミレが言う。
2人はチャリに跨がって、ゆっくりゆっくり、道をひた走る。
香がスミレとチャリに乗るのは久しぶりのこと。スミレは香が生まれる前から運転免許を持っていたけれど、東京に住んでいた時はほとんど車に乗らず、チャリかバスかタクシーか電車だった。沖縄に引っ越して来てからは毎日のように車に乗っている。沖縄に来てからスミレがチャリに乗っているところを香はほとんど見たことがない。
スミレが前を走り、香が後に続く。香は立ちこぎしてスピードを上げて、スミレに追いついた。
「ねえ、お母さん」
「うん」
「音がないね」
「あたしも全く同じ事考えてた」
2人が言う通り、その時、島には音という音の一切がなく、無音だった。風の音もなく、沖縄に住む声の高い蝉の声もなく、波の音もなかった。気持ちがいい、というのとはまた別の気持ちだったけれど、それを説明する言葉を香はまだ持ち合わせていない。
無音の中、会話なく2人はチャリで進んで行く。道はまっすぐ伸びていて、時折、左に直角に枝分かれする道があった。何度目かの枝分かれのポイントでスミレがブレーキを踏んだ。香も止まる。誰もいない農道に、ナンバーのない軽自動車が停車している。アザラシの死骸みたい、と香は思った。
そしてスミレが言った。
「二手に別れようか」
「いいよ」
「私、左に曲がってみる。この先の島の一番端っこで待ち合わせよう」
「わかった」
「カベールの植物群落っていうところ。ここから2キロくらいだから、20分もあれば余裕で着くよ」
「2キロなんて10分で着くよ」
香はスミレと別れて一人になって自転車を走らせた。隠れんぼみたいでウキウキしてきて、香は立ちこぎになる。道の途中に、「久高島カベールの植物群落」という案内板が立っていて、香はチャリを止めた。この先にあるはずのカベールの植物群落に自生する7つの植物についての説明書きがあった。「アカテツ」という名前の植物が香は気に入った。沖縄の言葉で「ちーぎ」。日差しは透明な針となって皮膚を刺す程だったけれど、香は元内地少女というよりドジンさんの子供としての自負があったので、痛いとも暑いとも思わないようにした。香は程なくして看板の前から去った。
やがて、道の終わりが見えて来た。
道の終わり、島の終わり、地上の終わり。
香は突然、重力が信じられなくなる。
空に落ちてしまうんじゃないかと錯覚して、怖くなる。
結局10分もかからずに香は島のはしっこに到着した。
チャリから降りた途端に暑さを感じ始める。日陰を作ってくれる樹木はひとつもない。香は帽子を一度脱いで、手櫛をして髪の毛の間に空気を通した。そして被り直す。
カベールの植物群落は天然記念物だったけれど、そこに自生している植物の色は全て緑色で、植物の形も香の目から見ると沖縄的雑草にしか見えなかった。
香は携帯電話でスミレに連絡する。電源が入っていないとアナウンスが流れる。来た道を眺めるが、スミレはやって来ない。
まあ、20分くらいってお母さん言ってたし。
そう思って香は大人しく待つことにする。
けれども香は時間の潰し方を見つけられない。
スミレがやって来ないことへの苛立ちと不安が、香から観察力や想像力や視野やニュートラルな思考を一つずつもぎとってゆく。カベールの植物群落が、名前を失くした待ち合わせ場所になりさがる。珊瑚礁やハマユーという名の花も香の目には映らない。遠くに
続く