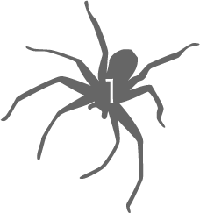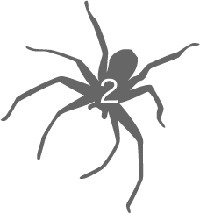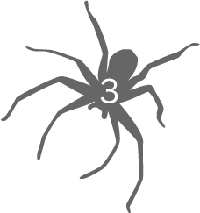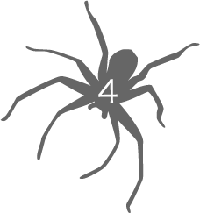熊坂 出
香の両親が離婚したのは香が4歳の時。家庭裁判所の審判で監護権は威が勝ち取り、スミレの元に預けられていた香が威に引き渡される時、スミレは香を諦められず、香の目の前で威と1時間の間怒鳴り合いをした。その間ずっと香は泣いていた。
スミレは香と離れて暮らし始めたが、全部が無理だった。その無理さはおそらく親でないと分からないもの。スミレは香という名の自分の人生と引き剥がされ、体重は容赦なく目減りしていった。スミレの身長は160センチあるけれど、体重は30キロまで落ちた。それでも仕事は続けた。スミレにとって仕事は私事で、スミレと翻訳はいつだって幸福な間柄だったのだけれど、この時ばかりはスミレは仕事に見放され、言葉から見放されていた。翻訳はするけれど、スミレフィルターを通して抽出された言葉の組み合わせになっていなかった。思考できていない自分に気がつくこともなかった。スミレの翻訳した言葉にはいつだって詩情があって、その詩情を外国の作家や出版社から買われていたのに、そうしたスミレの気配や残り香が翻訳した言葉から失われていた。仕事が減っていき、2ヶ月間に渡って暇を持て余した。何をする気にもなれなくなった。そしてある日、スミレは計画を実行した。香を誘拐した。
*
誘拐犯のスミレと香は2人で暮らすようになった。香はスミレが少しでも家を空ければ情緒不安定になり延々と泣き続け、かと言って一緒にいると、香は激しくスミレに反発しスミレを殴ったりスミレの髪の毛を引っ張ったりした。
そして再び、威に見つかってしまう。そしてスミレは逃げる。捕まる。威に引き取られる。そういう事が延々と繰り返された。まるで戦争みたいだった。幼い香はおねしょをするようになり、居間でおしっこをすることもあった。
そしてとうとう威が折れた。香にとってよくないと思い、威が折れた。威もまた香を必要としていたのだけれど、威はスミレと違ってお腹を痛めていなかったし、香が生まれたばかりの頃、一時間毎にお乳を与えるためほとんど徹夜だったスミレの苦労を完全には分かち合えていなかったし、威はそういう事、スミレ程香を育てるために自分を割かなかった事実を並び立てて、自分を納得させた。当の香は、スミレよりも威になついていたし、威も香もその事を自覚していたのだけれど、ある種2人は共犯関係となって、互いを諦めたのだった。
スミレは香を連れて沖縄へ引っ越した。スミレが引っ越しを繰り返すのは、引っ越しが好きと言うのももちろんあるのだろうけれど、いつ威がやって来るかという恐怖に怯えてるのもあると、香はずっと心の中で思っていた。香はそういう事を決して口にしなかったし考えないようにしていた。
「港のところにある待合室にいるから。来て」
「どういうこと? お母さんは?」
「分からない」
「は?」
「今日、久高島に香を連れて来るから、後は宜しくって言われたんだ」
香は頭が真っ白になった。
「どういうこと?」
「お父さんにも分からない」
「ごめん」
ふいに、謝罪の言葉が香の口から漏れた。
「なんで香が謝るの?」
「いや、なんとなく」
「なんとなくっておかしいよ」
香は泣きそうになったけれど、歯を食いしばった。
「心配ばかりかけて、ごめん。私とお母さんのことでいつも心配かけて振り回してごめんなさい」
香が泣きそうになったのは、自分の身に何が起こったのか既に察していたから。でも、それを認めたくないから言語化することを先送りにしていた。でも、心や脳は察知していた。香は大人にならなければならない。香が俊太や健太と自ら交わっていたのは、もしかしたら、本能的に今日という日を察知していたからかもしれない。
香は今まで、誰にも、どんなに親しい友達にも、母親との苦悩を打ち明けなかった。考えないようにしていた。考えてしまうと、自分を憐れむような涙が出てしまいそうで嫌だったから。自己憐憫という言葉を、香は小学校3年生の時に知った。教えてくれたのはスミレで、その経緯はまたいつの日か。
「香が謝ることじゃない」と、威は電話口の向こうで怒りを殺した声で言う。
「でもお母さんとの生活はけっこう楽しかったんだよ」
「分かってる」
香は口に出さなかったし、心の中でもその3文字を描かなかった。もし言葉にしてしまったら、泣いてしまうから。なんだってうちのお母さんはいつもこうなんだろう。
「畜生!」
と香は地面に向かって叫んだ。ゲンチャが見ている。
畜生、畜生、畜生、畜生、と香が叫ぶ。
捨てやがって、捨てやがって、捨てやがって、と香が叫ぶ。
ゲンチャの言うとおりだ。あたしはそんなにお母さんのことを知らない。知ってるけれど知らない。
電話口の向こうは無言で、ゲンチャも無言だった。
しばらくして、香が、電話の向こうの父に言う。
「いっつもお父さんが尻拭いしてるよね。ごめん」
「香は今、どこ? 迎えにいくから」
「大丈夫。そこで待ってて」
全然大丈夫じゃないけれど。香は心の中でそう言って一方的に電話を切った。
「なんで、助けを呼ばなかったば」
「ゲンチャが言ったんじゃない。そう簡単に大人の手を借りるなって」
ゲンチャは言い返せない。
「ゲンチャのお父さんは何してる人なの?」
「知らない」
「知らないって?」
「俺、おじいちゃんと暮らしてるから」
「お母さんは?」
「俺、捨て子だから」とゲンチャが会話を遮った。
香はゲンチャの目を見た。ゲンチャの眼差しはとても強く、香は思わず目を逸らしてしまった。
「お前も大変だな」と言って、ゲンチャは泣いた。香は吃驚した。
「なんで泣くの???」
「お前が可哀想だから」
「は?」
俺は生まれた時から傍にはおじいちゃんがいて、敬子さんっていうお母さん代わりの人がいた。敬子さんは俺が小学校に上がった時に死んでしまった。ずっと一緒だった人と離れるのは辛いよな。しかもお前は本当のお母さんとだろ? お前が可哀想だ。お前が可哀想だ。俺思うんだけど、大人はいつもそうだとか大人は分かってくれないとかいう言葉は間違っていて、大人も子供もなくて、皆、子供で大人だ。お前、さっき、大人だったよ。正真正銘の。大人だった。俺には分かるよ。
「あたしが可哀想かどうかは私が決める事だよ」
香はそう言って、ゲンチャは泣き止んだ。
「そうだな」
自分を苦笑したあの英語教師が、いつだったか言った言葉を思い出す。
汗と涙は自分のために流すのではなく、他人のために流すもの。努力とぼやきは隠れて流すもの。
香はその英語教師のことが大好きだった、理由はよく分からないけれど。だから、苦笑された時に、過剰に傷ついてしまったのだ、と今、思い至った。
日が暮れて来る。威から何度も着信があって、その度に香はいちいち応答ボタンを押して、自分は生きている事を暗に伝えて、通話終了ボタンを押す。
香はゲンチャに、沖縄で出会った2人の少年のことを話した。
俊太のこと。
健太のこと。
香は俊太のために料理酒を飲んで、健太のためにおならをした事を話す。
でも、結局、うまくいかなかった。
ゲンチャが言った。
「お前がやった事がうまくいったかいかなかったかは、お前が決める事じゃない。相手が決める事だよ」
「もし、余計なお世話としか思われてなかったら?」
ゲンチャが香の目をじっと見る。香は目を逸らさなかった。でも、ゲンチャは何も言わなかった。
あのさ、なんでお母さん探すの手伝ってくれたの?
敬子さんが死んだ時、後悔したからさ。
何を後悔したの?
ゲンチャは、分からない、というふうに首をひねって、岩場に横になった。
なんか、もっと話せばよかったって思ったから。ただ、それだけ。
俊太も同じことを言っていたな、と思い出す。
健太はあの子供とおしゃべりできたかな、と思う。
まだまだ太陽は空高いところにある。
ゲンチャのお腹はさっきからグーグーキュルキュル鳴っているが、「お腹すいた」とは言わなかった。岩が頭や背中に当たって痛いのだろう、一番寝心地の良い位置と姿勢を探している。その内、うつ伏せのヘンテコな姿勢になって、ゲンチャはそのまま動かなくなった。けれども、目は開いたままだ。ゲンチャを見つめながら、香は思う。
ゲンチャはきっと、痛いとか辛いとか悲しいとかあんまり言わないんだろうな。
この人は父と母がいない自分を特殊だとは思っていないだろうな。それがゲンチャにとって普通のことだったから。
香はゲンチャのところへ行くと、しゃがみこんで膝を伸ばし、ゲンチャの頭を剥き出しの膝の上に乗せた。ゲンチャは吃驚して香の顔を見るが、すぐに目を逸らす。香はゲンチャの髪の毛を人差し指で触る。ゲンチャの髪の毛は短髪でサラサラで、汗に匂いはなく、水みたいだった。香は膝の上のゲンチャを見ながら、口を小さく開けた。香の口から歌がこぼれた。その歌はニーナ・シモンだったけれど、子守唄として香は歌った。香の歌は途方も無く音痴だったし、香はものすごく恥ずかしかったけれど、ゲンチャを思って歌を歌った。ゲンチャはちょっと笑って、目を瞑った。また涙が出ていた。ゲンチャは泣くまいとしているようだったけれど、小さく嗚咽がもれ、その内、スースーと寝息を立てて眠りに落ちていった。ゲンチャの寝顔を見ながら、香は俊太の父親のことを思い、うああああおじいさんのことを思い、ゲンチャに子守唄を歌えなかったゲンチャの母親のことを思い、ふいにゲンチャが見たという熊のことを思った。
熊って、ひょっとしてお母さん?
ゲンチャが香の歌声が途切れたことに気がついたのか、寝返りを打ったので、香は慌てて音痴な歌を再開した。でも、ゲンチャは本当のところ、ぐっすりと眠っていて、この世界とは別のところにある無意識の世界を泳いでいた。
海も空も岩場も、海の中をちょっと見れば見つけることができる気味の悪いウミケムシも、香の音痴な歌声に耳を澄ますことなんてなくて、香は一人、ニーナ・シモンを歌った。小さな香は、どこへも誰にも届くことのない歌を、果てのない海を見渡しながら呟き続けた。
「いた!」と子供の声がした。
見上げると、島の子供達が崖の上にいる。島の入り口で挨拶を交わした小学生達と、見知らぬ中学生。
中学生の男子に負んぶされながら、香は、岩場に遭難した時にどうやって地上に戻ればいいかを教わった。香は「三点支持」という言葉を覚えた。自分はまだまだドジンには程遠い内地の人だ、と香は思う。
「なんで私達があそこで遭難してるって分かったの?」と香は聞いてみる。
「変な歌が聞こえた」と子供達は言った。
香はチャリに乗って、ゲンチャと地元の小学生達と共に港へ向かった。父が待つ場所へ。
けれども、その途中で、香はふいにチャリを止め、くるっと踵を返す。
「どこ行くば?」
「お母さんを探す」
「親捨てれ」と、ゲンチャが言う。
「一緒に探して」
香はゲンチャの手を握った。ゲンチャの手は柔らかくて女の子みたいな手をしていた。了